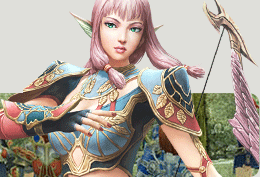第一時代:永遠の消失
プロローグ「流星雨」
円形の舞台の半分を囲んでいる7本の柱に、順番に火が灯った。
日が暮れて暗くなっていく空を背景に青く浮かび上がる魔法の光。
やがて、舞台の中心にある魔方陣がかすかに光り始めた。
客席からは低い嘆声の渦が巻き起こり、やがて静まった。
薄暗い照明に合わせたように、舞台の中央に立っている俳優は低い声で呟いていた。
そして徐々にその独白の声は大きくなり、強烈な叫びへと変わった。
それと同時に俳優の足元で舞台を飾っていた魔方陣がまるで光を噴き出すように光った。
両親の間に挟まれおとなしく座っていた幼い少女は周りを見回した。
少女には舞台の上での劇の内容よりは、客席の全エルフが感嘆の息を吐き、
涙を拭く姿の方がもっと興味深かった。
寿命が長く、精神の成長が早いのがエルフという種族の特長だが、芝居の中で
複雑に絡む人物関係や権力の流れなどを理解するには少女はまだ幼かった。
舞台の上で長い独白を行っている俳優が、エルフの文化・芸術の先頭に立つ人物であり、
大陸に住む誰もが彼を知っているほどの有名な俳優兼劇作家であること、
そしてエルフの歴史に刻まれる程の人物であることなど、この少女には何の意味もないことだった。
少し涙ぐんだ目を拭き、両親を見つめていた少女は何気なく空を仰いだ。
いつの間にか空を覆っていた夕焼けは、厚い闇の裾の下にその色を隠し、西の空の端に
かすかな光が残っているだけだった。
その時、尻尾のように長い光が一筋空を横切った。
ぼっーとして空を眺めていた少女は急に息を飲み込んでしまった。それに驚いた少女の母親は
心配そうに少女にささやいた。
「どうしたの、リマ?調子でも悪い?」
リマは首を横に振り、指で空を指した。客席を詰めていた全エルフの視線が分散し始めた。
観客はもう舞台を見ていなかった。舞台上の俳優もセリフを忘れ、夜空を仰いでいた。
夜空なのにもう暗くはなかった。数十、数百、数千。いや数え切れないほどの光が夜空を
横切り、大地の方へ溢れ落ちていた。誰かがつぶやく。
「……流星雨?」
リマは思いっきり首を振った。流星ではない、あれは貴い方の壊れた肉体、
最も偉大なる方の散らばった意志。
幼いリマは魂の彼方この真実をどうやって周りの人に伝えればいいのかが分からなかった。
リマのお母さんが微笑みながらリマにささやいた。
「本当に綺麗だわ…ね、リマ?」
しかし少女の小さな肩は震えていた。母親も父親も、周りの誰も気づいていない。
薄暗い森の中から、陰気な沼から、そして人の足が途絶えた海岸から
その身を動かし始めた奇妙な生き物達。
殺気溢れる怪物の目、見たことのない遥か遠くの平野、そしてその上に散らばっている
数多くの死体。
死にかけている男、泣き喚く女、失った家族を探す子供、悲鳴、血、折れた剣、壊れた鎧……
リマの頭の中に、混沌や闇が溢れるシーンが絶え間なく流れ込んできた。
目をしっかりとつぶっても、その悲惨なシーンは見えてしまう。
青ざめた顔でリマは母親にすがりつき、やがて声をあげて泣き出してしまった。
その日は大陸を創造した主神であり、全ての生みの親である「オン」がその意思や魂を失い、
消滅してしまった日だった。
そして後日、エルフの国「ヴィア・マレア」の大神官、そして女王となるリマ・ドルシルが始めて
自分の能力に自覚した日でもあった。
第1話
野原に生い茂っていた雑草は無残にも踏みにじられ、無数の足跡だけが残っていた。
倒れていない雑草には絡みついた血痕が固まっていて、
風が吹いてきても揺らぐことはない。
ここは誇り高いジャイアントに守られてきた大地。
そしてこれからも永遠に守っていく大地。
口でこう呟いてみたが、何年か前には心の奥から湧き上がってきた勇気も誇りも今はない。
丘の上に立っていれば広々とした野原が一望出来る。
「悲嘆の平野」と呼ばれるその野原は、モンスターの大規模攻撃に対抗したジャイアント部隊が
激戦を繰り広げた場所だった。
大勢のジャイアントがここを守るために若い命を落とした。
戦闘終了直後の撤収の際に立てられた簡素な墓碑が高く茂った草の間からその先端を見せ、
当時の戦闘の酷さを物語っていた。
あれから30年程月日が流れたが、状況は何も変わっていない。
2時間前までここでは激しい戦闘が繰り広げられていた。
そして今はその悲惨な跡がそのまま目の前に広がっている。
ジャイアントの若い兵士達が野原のあちこちに散らばっている仲間の遺体を回収したり、
モンスターの死体を集めて燃やす準備をする姿が見える。
ナトゥーは舌を打ちながら野原を見回した。
今回もこの地は無事に守られたが、モンスターはいつかまた攻撃してくるだろう。
奴らは絶え間なく数を増やし、居住地に入り込み人の命を狙い襲ってくる。
その目的さえも分からない、盲目的なモンスターの攻撃は、ロハン大陸の全種族に
永遠に消せない恐怖感さえ与えていた。
まるで永遠に続きそうな戦闘、また戦闘。
物心付いたばかりの年頃、奇怪なモンスターの群れがジャイアントの領地を攻撃してきたという
噂を初めて聞いた。
その時は立派な戦士になってジャイアントのために勇敢に戦うことが夢だった。
ナトゥーはその幼い頃の夢通り、今では若いジャイアントの中でも抜群の戦士に成長し、
まだ若いにも関わらず部隊長に昇進した。
しかし幼い頃の熱い情熱は失われ、今は習慣的に戦っているだけだった。
ナトゥーは丘の上から目の届くかぎりのところを全部見回したが、彼が探している姿は
見当たらなかった。
その不安感は彼の頭の中に暗い想像を浮かべさせ、彼は歯を食いしばり、眉間にしわを寄せた。
「大丈夫か」
後ろから聞こえたのは仲間のクレムの声だった。
クレムの方へ振り向いた瞬間、ナトゥーは熱い液体が額から顔の側面に沿って流れ落ちるのを感じた。
彼は額の傷に手を押し当てた。
臨時手当として緩く巻いておいた包帯は血液に濡れ、既に役目を果たしてはいなかった。
「こんな傷なんか……」
ナトゥーは愛想悪く答えた。
クレムは肩を大きくすくめて見せた。
彼の肩や腕にも血で濡れた包帯が巻いてある。
ジャイアントの中でも大柄だと言えるクレムの体には、長い歳月を戦場で生きてきた者らしく、
傷だらけだった。
それはナトゥーも同じだった。二人は15年以上も共に戦場で戦ってきた戦友だから。
「ラークが見当たらないな」
無情な言い方ではあったが、クレムはナトゥーと一緒に丘の下に広がる野原を見下していた。
彼も友人の弟が心配になっていたのだ。
野原の隅々まで見回したが、ナトゥーの弟は見つからない。
ナトゥーの表情が固まっていた。
クレムが聞いた。
「負傷して兵営のバラックにいるのでは?」
「いなかった。」
ナトゥーの声からは不安が十分感じられた。
クレムは再び肩をすくめた。
想像できることは二つだけ。
ナトゥーの弟は戦死したか、戦場から逃げたのだ。
勇敢なジャイアントの戦士なら戦場で死ぬことを選ぶ。それが一番名誉ある死。
仲間を捨てて戦場から逃げた者は一生消せない不名誉なレッテルが貼られる。
だが、家族や本人がその対象ならそれは簡単に判断することではなくなるのだ。
ナトゥーが落ち込んでいるのも当然だった。
戦闘、そしてまた戦闘を繰り返し、その名を全種族に知らせた勇敢なナトゥーにとって、
どちらがより酷いことなのか、クレムは横目で自分の友人を見つめた。
突然ナトゥーの口から長いうめき声が流れた。
ナトゥーの上半身は硬直し、下半身は脱力からふらついていた。
ナトゥーはゆっくりと足を運び、丘を降りていく。
やっと血の止まった額の傷がまた開き、彼の顔に流れた血が細い線を作っていたが、
彼はそれに気づいていないようだった。
ナトゥーの足が止まったのは、昔ここで命を落とした、名も知らない戦士のために立てた
墓石の前だった。
墓石に身を寄せて倒れている若い青年が見えた。
まるで激しい戦闘に勝利し、その場に座って休んでいるかのようだった。
勝利を収めたという満足感から笑っているのかもしれない。
だが、勝利の喜びで微笑んでいるはずの顔はどこにもなかった。
碑石に身を寄せていたのは、首が切られて頭の付いてない死体だった。
ナトゥーはその遺体の手首を握った。
その手首には金属で飾られた腕輪がかけられていた。
腕輪の金属は夕暮れの日差しを浴びて赤く光っている。
ナトゥーの表情が歪んだ。
彼は冷たくなった遺体を抱きしめた。
ナトゥーの手首の腕輪と金属飾りがぶつかり、泣き声のような音を出した。
それはナトゥーとラークの母親が、戦場に向かう二人の息子に渡した腕輪だった。
全ジャイアントの神であるゲイルに、幾日も夜を更かして祈った母親の愛情がこもったものである。
弟の遺体を胸に抱いたナトゥーの口から咽ぶような泣き声が漏れた。
クレムは苦虫を噛みつぶしたかのような顔で、空を仰いでつぶやいた。
「ジャイアントを守る偉大なる神、ゲイルよ。仲間の名誉のために戦い、
死を迎えたものがここにおります、彼の魂が神に戻り…」
「黙れ、そのゲイルが、神が一体何をしてくれたっていうのか!」
名誉ある死を追悼するための祈りはナトゥーの叫びのせいで途絶えてしまった。
そして、いつの間にか回りを囲んでいた若いジャイアントの戦士達が不安な表情で
ナトゥーを見つめていた。
ナトゥーは顔を歪ませたまま若い戦士達のほうへ振り向いた。
まだ少年の顔をした若い戦士達。
命を落とした自分の弟と同じぐらいに若い。
彼はこれまで数え切れないほどの若い戦士を見てきて、覚えられないぐらい多くの死を
見てきた。
今ここにいる者の中で、明日、そして明後日まで生き残れる者は何人いるだろう。
首の奥から熱い何かが込み上げてくるのを感じながら、ナトゥーは顔をうつむかせた。
いつしか彼は傍目を気にせず大声で泣き叫んでいた。
第2話
厚いカーテンは大きな窓の半分程しか隠していない。
長い窓の外からは、その堅固さで名高いグラット要塞の城壁、そして暗い夜空が見えている。
ほぼ満月に近い月が東の夜空に昇っている。
この世の母親、そして主神の伴侶であるエドネの瞳、月。
今夜はほぼ満月に近かったが、普段より冷たい青さで光っていた。
エドウィンは暖炉を眺めた。太い薪が月の光と対照的に真っ赤な色に燃え上がっていた。
松脂の香りが部屋中に漂っていたが、熱気はそれほど部屋を暖めていない。
松の薪に火をつけてそんなに時間が経っていないせいか、部屋はまだ少し肌寒い。
強くドアを開ける音がして、エドウィンは反射的に椅子から身を起こした。
彼は素早く腰を曲げ礼儀正しい姿勢でドアを開けた人を待った。
姿こそ見えなかったが、ドアの向こうに立っている者の高級そうな服装が垣間見えたからだ。
「顔を上げてくれたまえ、ここではそんなに硬くならなくてもいいのだから」
エドウィンは依然と礼儀正しい体勢を崩さないよう気をつけながら上体を起こした。
彼の目の前に立っている人は厚い布で作られた室内服を身にまとった、疲れた顔の老人だった。
痩せた体に窪んだ頬、上を向いている灰色の眉、頑固そうな印象だった。
きちんと鎧で武装した若い騎士が失望の表情を隠せないでいるのを見て、老人は微笑した。
「私がグラット要塞の総指揮官のヴィクトル・ブレン男爵だ。
今日中に支援兵力が着くことはないと思って寝ていたところだった。
こんな姿でがっかりさせて、申し訳なかった。」
男爵の服装は確かにエドウィンの期待とは違っていた。
なにしろ、ここはデル・ラゴスで最高の防御力を誇る難攻不落のグラット要塞だ。
総司令官もそれに相応しく武装した将軍だろうと思っていたエドウィンの失望を
和らげるのは彼の鋭い目つきだけだった。
エドウィンは首都の大神殿から預かった命令書を丁寧に男爵渡し、
一歩下がって待機の姿勢を取った。
硬苦しいほどに礼儀正しいこの若い騎士を男爵は興味深い目で眺めた。
“デル・ラゴス王国ロハ教団の聖騎士のエドウィン・バルタソンと、
彼が率いる見習い騎士2名をグラット要塞に派遣する。”
命令書は簡潔に書かれていた。男爵は頷きながらエドウィンの方を見た。
「貴君がエドウィンか。貴君のお父様であるバルタソン男爵には何回かお会いしたことがある。
次男が騎士団に入ったと聞いていたが、それが君なわけだ」
「さようでございます、閣下」
「閣下か…」
ヴィクトル男爵が大神殿からの命令書をテーブルの方へゴミを捨てるように投げるのを見て、
エドウィンは眉間にしわを寄せた。そして続く男爵の話に驚くしかなかった。
「閣下とかの呼び方はここでは止めよう。ここは騎士同士がお互いの命を握っている
最前線だし、私はこの要塞の全騎士が兄弟のように仲良く過ごしてほしいんだ。
今後は私をヴィクトルと呼んでくれたまえ」
エドウィンはどうすればいいか分からなくなった。
自分の父親の年齢に近い、ましてや上司である人を呼び捨てで呼んでいいのか。
騎士団の規律やルールが頑なに守られていた大神殿と聖騎士団での
生活に慣れているエドウィンに、彼の話は相当のショックだった。
その時、2人の目が合った。
年を取った総司令官には若い騎士の目からまっすぐな心を窺い知る事が出来た。
若い騎士は、武装していないにも関わらず目に見えないパワーを発散している、
総司令官のカリスマを肌で感じだ。
「よく来てくれた、エドウィン・バルタソン君」
「宜しくお願いします、ヴィクトル」
エドウィンはグラット要塞の総司令官に、左の胸元に拳を当て騎士団の敬礼を行った。
そして2人の騎士は同時に微笑んでいた。
総司令官の執務室を出て、要塞の中庭に出た時、庭の向かいに神殿が見えてきた。
この神殿はヒューマンを創造した神ロハではなく、
そのロハを創造した主神オンや母神エドネのために建てられた神殿だそうだ。
月は空の中央近くまで来ていた。
その青い光を浴び、質素で丈夫そうに見える要塞の壁が庭に影を落としている。
デル・ラゴスの首都アインホルンにある大神殿は知恵の神ロハのための神殿だった。
最前線のグラット要塞にロハのためではなく、
オンやエドネの神殿が建てられていることはどこか不思議な感じがした。
エドウィンは溜息をついた。
とにかく、これから彼はここで聖騎士として、兵士として生きていかなければならない。
思わずロハへの祈りの一行をつぶやいた彼は少し戸惑った。
そしてオンやエドネへの祈りをあげた。
夜空に浮かんだ瞳、エドネの瞳はただ黙ってこの大地を見下ろしているだけだった。
第3話
エトンは一国の首都であり聖地であった。
最初にロハン大陸に足を踏み入れた8人のジャイアントは、
この大地から得られた物を集めて神への感謝祭をあげた。
ジャイアントを創造した大地の神ゲイルはその場にその姿を現しジャイアントを祝福した。
そして、この荒れた大地を統治し、全ての存在がジャイアントに従うようにすることを命じた。
その場所がジャイアントの首都、エトンである。
きめ細かく飾られた王宮はジャイアントの中でも長身な方であるナトゥーにさえ
威圧感を感じさせた。
いつもその勇壮な美しさに感心していたが、今日のように誇らしく思えたことは初めてだった。
ジャイアントがロハン大陸に姿を現せてからかなりの歳月が経った。
しかしこの広い大陸の中でジャイアントが支配している領域はごくわずか。
この大陸を支配しその栄光をゲイルに捧げるどころか、
日々その数を増加させるモンスターから今の領域を守るだけで手がいっぱいだった。
「ナトゥー?」
クレムが低い声で呼んだ。彼はアゴで王宮の方を指した。
ナトゥーは軽く頷き、クレムと王宮入口に続く階段に足を運んだ。
最近、クレムはずっとナトゥーの様子を伺っていた。
また、ナトゥー自身もそれに気づいている。
弟のラークの戦死後、自分で気づくほど精神が不安定だったからだ。
「戦士会からの理由もないお呼びってどういった用件なんだ。」
クレムは少し心配げにつぶやいた。ナトゥーは肩をすくめて見せた。
実は彼は戦士会からの呼び出しより、
その後に母親と会うことになっていることがすごく気になっていた。
戦死した弟のことで悲しむ母親の顔を見るのはつらい。
弟の死が誇り高いものだったということは母親には何の意味もないことだろう。
結局頭を見つけられなかった弟の遺体が思い浮かんだ。
その遺体ですら持って来ることが出来なかったことも
母親にとってはなんともいえない悲しいことだろう。
ナトゥーは腕につけた二つの腕輪に優しく触れた。
一つは自分のもので、もう一つは死んだ弟のラークのものだった。
戦士会の集会室の方に歩きながらナトゥーは二つの腕輪があまりにも重く感じられた。
戦場で振るう二つの剣よりもっと重く感じられた。
状況の報告が終わるや否や戦士会は解散した。
ナトゥーとクレムは戦士会がすぐ終わったことに安心しながらも、
状況の報告のためだけに戦場で戦っている部隊長を呼んだことに腹をたてた。
二人は苦笑いをしながら集会室を出た。
集会室のドアの前にはまだ少年の顔をした青年が立っていた。
彼は二人に近づき、会釈した。
「ノイデ様のお呼びです。」
小声で囁く青年からは回りの目を避けようとする気配が明確に感じられた。
戦士会は解散したのに、戦士会の首長に呼ばれる理由はなぜだ、と聞きたかったが、
その青年はそれを聞く間も与えてくれない。
いつの間にか歩き始めた青年の後を追って、
ナトゥーとクレムは戦士会の裏にある小さな部屋に向かった。
戦士会の首長であるノイデは戦場での豊富な経験を持ち若者に負けない体力の持ち主だった。
もう戦場に出ることのない老いた将軍だが、若者に負けないがっしりとした体つきに、
経験からの賢明さまで備えた者だ。
およそ10年前、モンスターとの戦闘時に片目の視力を失い、
残った片目は腰につけた破壊力のありそうなセプターと共に前より鋭い力を発していた。
ノイデはその鋭い片目でナトゥーとクレムを観察するかのように眺めた。
彼の顔からは二人を迎える嬉しさなどは少しも伺えなかった。
ノイデは二人の戦士の挨拶を適当に流し、口を開いた。
「君らをここに呼んだのは、何年経ってもまったく変わっていない戦況報告のためじゃない。
特別な指示があるためだ。」
ナトゥーは唇を噛み、クレムの顔は悔しさに歪んだ。
二人の戦士が命をかけて守っている戦場をあまりにも軽んじる発言だった。
二人の顔に不満の表情が浮かんでも、ノイデの冷ややかな表情が変わることはない。
彼は話を続けた。
「ダークエルフ側から使者が来る予定だ。君達に彼らの護衛を任せたいんだ。」
「護衛…ですか」
ナトゥーは怒りを押し込めた声で聞いた。
使者の護衛のために、部隊長の自分やクレムを首都まで呼ぶのはいくらなんでもおかしい。
何かの過ちで謹慎措置が下りたのでもない。
おかしいところはそれだけではなかった。
「その使者は私達が護衛に当たるほど大事な客ですか」
こんどはクレムが聞いた。
ジャイアントにとってダークエルフは嬉しい客ではない。
単純でストレートな性格のジャイアントにとって、形を重視し、
本音を出さないのが特徴のダークエルフは決して理解できない存在だった。
しかも彼らはジャイアントには分かることのできない力、魔法を使う種族。
そうした複雑な不快感がクレムの短い質問に込まれていた。
ノイデはもう一度2人の戦士を見つめ、頷いた。
「君達の活躍ぶりはすでにここエトンまで知られているから、
君達はもうすぐ戦士会の一員になるだろう。
だから知らせておく必要があると思ったんだ。
偉大なる戦士で、岩の魂を持つ我々の国王、
レプトラバ陛下はダークエルフと手を組もうとお考えになられている。」
2人の若い戦士は驚いた顔のまま、何も言えず口ごもってしまった。
彼らを見つめていた老いた戦士の口元にほんの一瞬かすかな微笑が浮かび、すぐ消えた。
第4話
少女は泣き止んでいたが、まだその顔から涙の跡は消えていなかった。
そしてその瞳は固い決意で光っていた。
少年はそんな少女の顔を見るのが苦しかった。
少女が、今日の昼間と同じく怒り出し、泣き叫びながら少年の父親を非難した方がずっとマシだと、
少年は思った。
雲が月を隠し、闇の帳が色濃くおりて足元も見えない夜道を少女はすたすたと歩んだ。
闇が濃く、少年には少女の姿が半分ぐらいしか見えなかった。
その後姿が物悲しくて、少年は普段は行こうと思ったことのない暗闇の道を、
少女の後を追って歩き出した。
町外れの家屋を過ぎても歩みを止めず、そのままかなりの距離を進んだ後に、
少女はようやく振り向いた。
漆黒の闇の中であっても、少女の怒りがまだ収まっていないのが十分伝わってきた。
少年は声をかける事も出来ず所在なさげにゆっくりと足を止めた。
その時、月が雲の隙間から顔を見せた。
月明かりで見えた少女の顔は涙で濡れていた。
口を硬く閉じて少年の方を睨みながら涙を流していた。
少女は少年に叫んだ
「あなたのお父さんがうちの母さんを殺したんだ!」
エドウィンは刺すように痛む頭をじっと手で押さえながら体を起こした。
窓は閉じているのに、うるさい鐘の音が部屋中に響いていた。
彼は頭を軽く振るい夢の余韻を頭から消し、窓の外を見た。
まだ夜明けの薄い青色の闇が漂っている要塞内は耳が痛くなるほどの鐘の音や、
その音のせいで目を覚ました兵士達のざわめきで騒然としていた。
1人、2人と要塞の中庭に集まり始める兵士達を見て、
エドウィンは服を適当に身に纏い剣を手に握るやいなや、部屋から駆け出した。
鐘の音は要塞の中央にある神殿から聞こえてきた。
神殿の塔の天辺にかかっている銅の鐘が壊れそうなほど揺れていた。
要塞の兵士達は神殿の周りに集ったまま戸惑っている。
エドウィンは自分の目が届く範囲を見回した。
兵士達の視線が神殿に向かっているのを見て、外部からの襲撃ではないと判断した。
神殿の前にはエドウィンと一緒にグラット要塞に派遣されてきた
見習い騎士のハウトが立っているのが見えた。
彼も鐘の音に驚き急いで駆けつけてきたようで、服装がずいぶん乱れていた。
エドウィンと目が合ったハウトは目で神殿の門を指して見せた。
神殿の門は硬く閉められていた。
何かがおかしい。
神殿には鍵をかけていないし、通常は寒い冬の日であっても門は開かれているのだ。
神殿は誰にでも開放された場所だからだ。
しかし、今要塞の神殿の門は誰かが入るのを拒むように固く閉じられている。
そしてその閉じられた門の内から、鐘の音が依然として激しく鳴り響いているのだ。
エドウィンは大きく深呼吸して剣を握りなおした。
エドウィンとハウトはそっと、神殿の門に近づいた。
二人の騎士は門の取っ手を1つずつ握り、思いきり力を込めた。
開けられそうになかった厚くて重い門は意外と簡単に開く事が出来た。
夜明けの弱い光が神殿の中を照らす。
そしてその光に背を向けた人が1人、空中に浮かんで揺れていた。
首を綱で絞められて、四肢がだらりと垂れ下がっている。
死体だ。
神殿の一番奥にある広い一室には、オンやエドネの石像が安置されていた。
銅の鐘から垂れていた綱にかかっている死体は、
奥に見えるオンとエドネの石像をその体で隠すように激しく揺れていた。
はっと動きが止まっていたエドウィンは、神殿の中へ駆けつけて、
揺れる死体の動きを止めた。
鳴り続けていた鐘はさらに数回弱い音色を発した後、ようやく止まった。
エドウィンはその死体を抱いたまま神殿の外の方を見た。
ひどい衝撃を受けたらしく、ハウトは崩れ落ちるようにその場で座してロハに祈っている。
エドウィンは彼に向かって大声で叫んだ。
「ハウト!騎士達を呼んでこい!今すぐだ!」
ハウトはもがきながら立ち上がり、後ろに下がった。
そしてやっと騎士団の詰め所の方へ走り出した。
エドウィンは死体から離れて少し後ろに下がった。
たぶん自分の顔もハウト同様真っ青になっているだろう。
エドウィンは自分が動揺している事に気付いてはいたが、
すぐに鎮める事は出来なかった。
彼はまだ自分の目で目撃したことが信じられなかった。
まだ夢を見ているのかとも思った。
グラット要塞の総司令官ヴィクトル・ブレン男爵が、
胸に大きな穴が空いた遺体となり、
鐘の綱に吊り下げられ揺られていたのは現実の事なのか?
エドウィンは何人かの兵士と力を合わせヴィクトル男爵の死体を綱から外して床に降ろした。
当直中だったのか、武装したままの兵士が、
自分のマントで総司令官の遺体を覆い、目を瞑らせた。
遺体が見えなくなったことで、ようやくエドウィンは気持ちを落ち着かせる事ができ、
壁に体をもたれかけさせた。
男爵の遺体には不審なところがたくさんあった。
だが、グラット要塞に派遣されて1日も経っていない自分が
今回の事件の調査で表に立つ事は出来ないだろう。
彼は目を開けて神殿の外の方を眺めた。
集めていた兵士達が3、4人ずつ群がりざわめいていた。
何かが…おかしい。
騒いでいる兵士達を落ち着かせて整列させ、
この事件の後始末をすべき騎士達の姿が見えない。
それ以前に、普段ならこの時間になると朝の業務を指示し、
訓練の準備で忙しいはずの騎士達が1人も姿を見せない。
しかも、今朝はうるさい鐘の音や叫び声で、
普段よりうるさくて騒がしい朝だったはずだ。
…なのに騎士は1人も見当たらない。
緊張と不安でエドウィンの顔が強張ってきた。
そういえば騎士達を呼ぶために詰め所へ向かわせたハウトもまだ戻ってこない。
エドウィン気付いた、この要塞で何かが起きている・・・
兵士達の方を見ると、彼らも何かがおかしいと感じ取り、騒いでいるようだった。
やがて兵士達のざわめきもだんだんと小さくなり、
彼らは騎士団の詰め所の様子を伺っているようだ。
エドウィンは手に提げていた剣を握りなおした。
皆が眠っていた夜、騎士団の詰め所をモンスターが襲ったのか。
この要塞にいる騎士はもう自分だけかもしれない、という不安が頭を横切った。
…自分の目で確かめるしかない。
もう夜は明け、辺りを覆い隠すような闇も消えて太陽が昇っている。
雲1つ浮かんでいない青空に鎮座する太陽からまぶしい日差しが
溢れているのにもかかわらず、不安は消えない。
エドウィンが閉ざされた騎士団の詰め所のドアに手を当てようとした瞬間、
どこからか声が聞こえた。
その女性の声はヒューマンの言葉を喋りなれていないように、どことなくぎこちない。
また、その声はエドウィンの耳ではなく、彼の頭の中に入り込んできたようだった。
-大丈夫?私の声、聞こえていますか?-
第5話
ナトゥーは自分がジャイアントという事に誇りを持っていた。
また、自分が優れた戦士の1人として認められている事に誇りを持っていた。
そんな彼にとって、ダークエルフという異種族はとても奇妙で、
気まずさまで感じられた。
形容詞をたくさん使う言葉遣いや派手な服装はともかく、
ダークエルフ男性の女っぽい仕草は見ていられない。
彼らの手の動きはジャイアントの女性よりもなまめかしく見える。
そんなナトゥーだからダークエルフ使者団の護衛という仕事には不満が多かった。
そんな事より、危険な戦場で生き残るために剣を振るい、
敵を倒し続ける方が彼の性に合う仕事だった。
しかし、首都エトンの戦士会から任せられた任務を拒否する権利は彼にない。
特に、もうダークエルフの使者団と合流後のこの状況では。
使者団は予想より小規模だった。
高飛車で偉そうに振舞うダークエルフの女性を中心に、護衛役の若い男性5人。
ナトゥーやクレムの部隊が配置されていた戦線の近くで彼らと合流し、
二日ぐらい一緒に移動しているうちに、
少しずつダークエルフの顔立ちになれてきた。
ダークエルフはジャイアントとは少し距離を置き、
必要以上に親しくならないようにしているらしかったが、
その中の若い1人は、ジャイアントという種族を始めて見たらしく、
興味を惹かれている様子だった。
彼は傍目にも分かるほどジャイアントを観察していて、目が合うと、にこりと笑った。
そんな柔らかい態度になれていないジャイアントの戦士達は、
その若いダークエルフ青年の行動にどう反応すればいいのか分からず困っていた。
使者団を護衛し始めてから3日が経った日、
泊まっていたキャンプから出発してから間もなく、
ナトゥーはクレムに近づいてこう言った。
「ちょっと先に行って状況を見てくる」
「先発隊との連絡を君がやる必要はないだろう、下の者を送れよ」
「いや、俺が行く」
クレムは顔を顰めた。
ナトゥーはクレムが反論のために適当な言葉を探している間に、
ライノに乗って先へと進んだ。
ナトゥーはダークエルフの態度を気まずく感じていて、
彼らと話すことさえ避けたかったのだ。
それでダークエルフと一緒にいる時間を減らすために、
先発隊の状況を見る、という口実で 使者団との距離を開けていた。
クレムはそんなナトゥーを不満に思っていたが、
指摘するタイミングをずっと逃していたし、
クレムの気持に気付いていたのであえて黙っていた。
使者団から離れて先方を走っていたナトゥーは急に手綱を引いて速度を落とした。
誰かが自分の後ろを追いかけてきている。
まさか…クレムがうるさく小言を言うだけのために、
ここまで追いかけてくるはずはない。
振り向くと、思ってもいなかった顔が見えた。
ナトゥーを追いかけてきたのはダークエルフ使者団の1人、
好奇心旺盛なあの若い青年だった。
彼は全速力で追いかけてきたせいか、短い距離だったにも関わらず息が荒い。
白い息が彼の口から冷たい空気の中に広がり、すぐ消えた。
「すごく早いですね、追いかけるの、けっこう大変でしたよ。」
好意溢れる微笑を浮かべるダークエルフ青年を、
ナトゥーは眦を吊り上げ睨むように眺めた。
ナトゥーは愛想悪い言い方で答えた。
「危険だから戻って早く一行と合流するんだ。」
「あなたは確か、ナトゥーっていう名前でしたよね?
ジャイアントの国でも有名な戦士ってお聞きしました。
あなたと一緒なら危険じゃないですよね?」
「戻れと言ったはずだ」
「あなたを信じてますから」
ナトゥーがいくら険しい表情で言っても、
のれんに腕押しといった態でその青年は微笑むのみ。
ナトゥーはため息をついて、ゆっくりとヒポグリフを歩かせた。
兵士達が先発隊としてモンスターを倒しながら道を作っているから、
危険なことが起きる可能性はほぼ無いはずだった。
ダークエルフの青年はナトゥーの隣に並びヒポグリフの手綱を握った。
青年が身に纏っている厚いコートや、
彼の顔を半分程隠している帽子が相当な高級品であることは、ナトゥーにも分かった。
‘護衛員のくせにおめかしか?
…ったく、ダークエルフっていう奴らは…‘
ナトゥーの視線を感じたのか、
青年はナトゥーの方を見て、またにっこりと笑った。
「そういえば、自己紹介していませんでしたね。
私はフロイオン・アルコンといいます。皆フロンって呼ぶけどね」
長い名前をわざわざ付け、そのわりにそれを略して呼ぶのは、
ジャイアントにとって慣れない文化だった。
‘どうせ短くして呼ぶのなら、最初から長い名前なんか付けるなよ‘
フロンと呼ばれるその青年は、
何かの反応を待っているように横目でナトゥーを見つめながら、
顎を撫でたり毛の付いた帽子を被りなおしたりした。
それでも無反応のナトゥーに彼はがっかりしたようで、
それからは周辺の風景を眺めていた。
諦めの早い性格なのか、
もしくはナトゥーも何回か経験したダークエルフ特有の見栄張りなのかもしれない。
「ここってすごく寒いですね。
あなた達ジャイアントはそんな格好で、寒くないのかな?」
「…慣れているから」
フロンには薄い服装のナトゥーが不思議に思えたが、
ナトゥーには毛皮を身にまとい暑く重苦しそうなダークエルフの格好が
馬鹿らしく思えた。
ロハン大陸南方出身のダークエルフに、
ジャイアントの領地である北の地域の寒さは耐えられない。
そういった違いだけでなく、両種族はあまりにも違う。
なのに、どうしてダークエルフは俺達ジャイアントと手を組む気になったのか
…とナトゥーは思った。
「私たち使者団がドラットを訪問する理由は何なのかご存知ですか?」
フロンの急な質問に、ナトゥーは自分の考えていたことが読まれたような気がした。
不快さを感じて彼を睨んだが、
フロンは依然と柔らかい微笑を浮かべていた。
「私達、ダークエルフはあなた達を北方の未開種族と呼んでいます。
たぶん、あなた達ジャイアントも似たような汚い言葉で私達を呼んでいるのでしょうね。」
事実だった。
しかもダークエルフが呼ぶ北方の未開種族という表現より、
ジャイアントがダークエルフを呼ぶ言葉はもっと汚い俗語である。
子供や女性の前では口に出す事もできない表現だった。
その言葉が頭の中に浮かんできて、ナトゥーは少し困った気分になり頭を掻いた。
フロンは顔色ひとつ変えずに話を続けた。
「しかし、私達とあなた達ジャイアントには共通するところがあるんです、
すごく大事な共通点が」
「共通するところ?」
「嫉妬からの憎悪、そしてドラゴン消滅以来、
この大陸を手に入れようとするヒューマンへの憎悪、そして…」
フロンは言う必要ないことまで喋ってしまった、
というように舌を打ち、そのまま黙ってしまった。
ナトゥーはフロンをまっすぐな目で凝視しながら言った。
「ダークエルフとは、国家間の秘密協定のように重大な事も、
護衛役の者にまでしゃべるようだな」
フロンの目が、まるでいたずらを企んでいる少年のように光った。
彼は馬の向きを変えて、どこか分からない方へ適当に手を振った。
「やっぱり仲間がいるところに戻りましょう、
寒くてきついですしね」
フロンはナトゥーに止める間も与えず、自分の仲間の方へ馬を走らせた。
ナトゥーは身勝手なダークエルフ青年に不快さを感じるより先に
あきれてしまい、肩をすくめた。
第6話
不意に頭の中に直接届くような声が聞こえた。
エドウィンは反射的に後ろを振り向いた。
振り向いたが、その独特なアクセントを持つ声の持ち主はそこにいない、
ということを直勘で分かっていた。
しかし、緊張で身体が張り詰めていたので反射的に振り向いてしまったのだ。
神殿の表や訓練場に集まっていた兵士達にはその声が聞こえなかったらしく、
依然として小さな集団がそこかしこに出来、総司令官の殺害事件について
話し合っていた。
エドウィンはその声がまた聞こえてくるのではないかとしばらく耳を傾けていたが、
何の声も聞こえてこなかった。
幻聴だったのか。
彼は肩をすくめて騎士団の詰め所に入った。
普段ならこの時間の詰め所は騎士達の声で騒がしい。
しかし今はまるで廃墟のように静かだ。
彼の背後で重たくきしむ音を立ててドアが閉ざされた。更なる不安が彼を襲う。
神経が極端に尖っているせいか、彼はたまに会議室としても使われるホールから
聞こえる小さな足音に気付いた。
エドウィンは剣を握りなおし、音が聞こえてくる方へと足を運んだ。
ホールのドアも硬く閉ざされていた。
ドアの取っ手を握ろうと、そっと手を伸ばした。
彼の手が取っ手に届く前に、ドアはエドウィンの方へ滑るように開け放たれた。
ドアの内側に身をもたれかけさせていた者がエドウィンの目の前に崩れ落ちる。
死骸が放つ生臭い血の匂い。彼はドアの隣の壁の方へ隠れた。
足元に転んできた遺体はハウトだった。
彼も神殿の中で吊られていたヴィクトル同様、胸に大きな穴が開けられ死んでいた。
急襲を警戒しながらホールの奥を見たエドウィンはその光景に息を飲んだ。
グラット要塞の全騎士がホールに集まっていた。
彼らは皆、騎士団の紋章が刻まれたプレートメイルや武器で武装していた。
そして皆、ホールの奥に向けて跪いている。
そして彼らの前の方には全身から光を発している者が見えた。
目の前が真っ白になった。
エドウィンはこの世界で最も輝かしい存在を目にしていた。
これまで一度も見たことはないが、今この瞬間、
彼はその存在が何なのかすぐ分かった。
地上に存在するものの中でもっとも荘厳たる存在。
全ヒューマンの神、ロハだった。
いつの間にか彼の体から力が抜け、ゆっくりと跪くような形を取った。
その瞬間、誰一人声をあげないその静まった広間に響いた金属音で彼は
気を取り直した。
体の力が抜け、握っていた剣を落としてしまったのだ。
床に落とした剣に目を向けると、またさっきの声が頭の中に聞こえてきた。
「…ですか、ご無事?私の声が聞こえる?」
「もう手遅れかも知れないよ」
先ほどの独特ななまりの女性の声とともに聞こえてきたのは甲高い声だった。
人の声とは思えないほど甲高く、
独特なイントネーションで何を言っているのか分かりづらい。
あわてているような女性の声に比べて、甲高い声は落ちついている。
すくなくとも、その2人の声はエドウィンが目にしている信じられない場面から
彼の目を離れさせることには成功した。
エドウィンは緊張で枯れていた喉からやっと声を出した。
「だ、誰だ。誰がしゃべってるんだ」
「私はトリアン・ファベル、高貴なエルフの女王、
シルラ・マヨル・レゲノン陛下が治める国ヴィア・マレアの国民で…」
「おいおい、そんな丁寧に自己紹介する時間はないって言ったろ?」
少し緊張した感じの女性の声に続き、彼女の声を止める甲高い声。
おかしくて笑いが漏れそうだった。甲高い声の人が話を続けた。
「そこにいるヒューマンの坊や、そこの状況を教えてくれないか。
彼は現れたのか?」
「…彼?」
エドウィンは直勘で「彼」が誰を意味するのか分かった。
今エドウィンがやっとの事で目をそらしているあの存在。
あの存在と目が合えば、たぶんエドウィン自身も跪いている騎士達同様、
服従して跪いてしまうに違いない。
全ヒューマンの神、ロハに。
エドウィンはまたホールの奥を覗いた。
ホール中央に立ち絢爛と輝いているその存在は、
彼が神の話や教理の本で見た絵の中の、神殿に描かれている壁画の中の、
そして神の石像の、そのロハと同じ姿だった。
眺めただけでも神聖な気が十分感じられる。
しかしその顔が浮かべている残酷な笑みや血だらけの手は、
エドウィンにとって、騎士達のようにその前に跪くわけにはいかない原因になっていた。
あの血まみれの手は…、あの手でハウトを殺したのか。
何故?何故ハウトを?
ヴィクトルもハウトのようにやられたんだろうか。
「坊や、応えろ!急にしゃべれなくなったのか!」
尖った甲高いその声がまた聞こえた。
そしてすぐその声の持ち主を責めるような女性の声。
エドウィンは小さな声で答えた。
「ここに…ロハ様が現れました、騎士団のホールに…」
「よく聞け、坊や。そいつは偽者だ。近づいちゃ駄目だぞ。
この要塞はもう終わりだ。逃げるんだ、要塞の外へ全力で走れ!」
甲高くまるで金属がぶつかるように冷たい声で、そして冷静な言い方で伝えた。
だが、混乱していたエドウィンの頭の中は、ただ1つのことだけを考えていた。
「あいつが…神の偽者がヴィクトルとハウトを殺したのか!」
エドウィンは落とした剣を拾い、しっかりと握り締めた。
深く呼吸をし、それと同時にホールの中へ飛び込んだ。
いや、飛び込もうとする瞬間彼の肩を握る手があった。
骨と皮だけのように痩せ衰えた、鳥肌が立つほど冷たい手だった。
第7話
世界を創造した主神オンは各種族の住んでいる大地の境に
強力なドラゴンを配置し、大陸の各種族が混ざらないようにした。
これはトリアンが子供の頃から神殿や学校で学んだ世界創造の神話の一部だった。
そのため各種族は、お互いがこの大陸のどこかに住んでいることに
気付いているにもかかわらず、主神オンの意志により、
長い間お互い会うことはなかった。
そしてロハン暦240年、ヒューマンの使節団が種族の中では初めて、
エルフの国ヴィア・マレアの首都レゲンの地を踏んだ。
境界を守護していたドラゴンが消えたという事実はこれを機にエルフ社会にも広まった。
どうしてドラゴンが消えたのか、どこへ消えたのかは明らかになっていないままである。
トリアンはちらりと、自分の道連れを振り向いた。
彼女の道連れのキッシュはデカンという種族だそうだ。
自らをドラゴンの末裔だと呼ぶ者達。
デカンという種族がこのロハン大陸に始めて現れたのは、
ドラゴンが消えた時期と一致していた。
だが、ロハン大陸の人のほとんどはデカンの主張を馬鹿な話だと思っていた。
トリアンもデカン族自らが主張する、ドラゴンの末裔という話を信用してはいなかった。
とりあえず、デカンはトリアンがこれまで見てきた絵や読んできた本が説明していた
事実とは色々なところが違っていた。
ドラゴンとデカンの一致するところは、鱗と鰭のような奇妙な耳ぐらいだった。
いや、トリアンが直接会った事のあるデカンは、
今彼女の目の前にいるキッシュ唯一人だったから、
他のデカンがどんな姿をしているのかはまだ分からないことだった。
トリアンはキッシュの視線を追って、グラット要塞の高い塀を眺めた。
些細な物にまで美しさを重視するエルフにとって、
ただ効率だけを考えた厚い壁を建てるということは理解できないことだった。
エルフのトリアンにとってグラット要塞は、美しさの欠如した冷たくて高いだけの、
草一本生えない岩の山のようなものだった。
しかもその厚くて高い壁は今、トリアンとキッシュには大変邪魔なものになっている。
2人はグラット要塞から少し離れた丘の上に身を隠していて、
要塞の中の状況を知ることはできないでいる。
キッシュは要塞の中の状況を調べるために、
トリアンには分からない特殊な能力を使った。
遠くに離れていても、目に見えなくても、要塞の中の声が聞ける能力だった。
キッシュだけでなく、トリアンまでその声の持ち主と会話できるようになる能力で、
キッシュはその能力をドラゴンの末裔の一部だけが使える特殊な能力だと言った。
が、トリアンはそれがエルフに伝わっていない魔法なのか、
何かのトリックなのかは分からなかった。
キッシュの能力で要塞の中の1人と会話をしていたのもつかの間、
トリアンにはもう、要塞の中の人の声やその周りの音が聞こえなくなった。
それはキッシュも同じだった。
キッシュの大きくて広い耳が2回、ひらひらと動いた。
彼は顔をしかめながら言った。
「その坊や、危ないかも」
キッシュはトリアンに答える間も与えず、要塞の方に向かって丘を下っていった。
トリアンは溜息を付きながらその後ろを追った。
どうしてこんな仕事が私に任せられたのか。
彼女はこれまで何度も頭の中に浮かべた疑問をまた浮かべていた。
ヴィア・マレアの首都ヴェーナは5つの区域に分かれている美しい都市。
そして魔法アカデミーはその5つのうち、一箇所全体を占めるほど重要な場所だ。
長い魔法の歴史の象徴である魔法アカデミーは、
海を後ろにそびえたつ王宮の塔ととともに、ヴェーナの誇りだとエルフは思っている。
円形に配置された建物の間の中央にある魔法アカデミー広場は、
学問を学ぶ場にふさわしく静かだった。
海の方から吹いてくる風に、広場内の木が揺れ、清涼な音を立てていた。
風が吹き、木が揺れ、鳥の鳴き声が聞こえる中でもリマ・ドルシルの声は
はっきりと聞こえてきた。
「お願い、トリアン。あなたは優秀な生徒で、才能ある魔法師です。
私の杞憂にすぎないならいいのですが…
そんなに簡単に終わることではないと思います。
あなたに手伝ってほしいのです。」
こんなことだと知っていたら断ったのに・・・。
この仕事を頼んできたリマ・ドルシルがヴィア・マレアの最高神官であっても、
リマ・ドルシルと魔法アカデミーの校長がトリアンの実力を認め推薦したとしても、
他に適任者を探して欲しいと断ったのに。
何故か楽しそうなキッシュとは違って、
トリアンは誰かと戦わなければならないということ自体が嫌だった。
エルフにとって人に怪我させたり、
人から怪我させられたりすることよりも不快なことはない。
要塞の入口から近いところに岩のでっぱりや草の藪があった。
キッシュはそこに身を隠し、トリアンを待っていた。
彼は急に真剣で怖い表情になり要塞の奥を覗いていた。
やがて着いたトリアンは要塞の奥から流れてくる気により、
息が詰まってよろけてしまった。
それは神の力や自然の気運を利用した魔法を使うエルフには
耐えられないほど暗い気運だった。
神の気運、しかし神聖さを失った暗い気運。
大神官リマ・ドルシルの話は事実だったのか。
「神々はもう私達に背を向けるでしょう。私達を恨み、
その恨みから私達をこの世から消そうとするでしょう。」
トリアンは体が震えてくるのを感じ、自分の肩を抱いた。
キッシュはトリアンをちらっと見て、長い指で要塞の中を指した。
要塞の入口は通常ではありえないほど開け放たれていた。
そしてその中には幾つかの影が動いていた。
吹いているのかどうか気付かないほど弱い風に中に、生臭い匂いが混じっていた。
血の匂いだ。
何故かヒューマンの兵士達はお互いの命を狙い、
凄惨な戦いを繰り広げていた。
キッシュがトリアンの肩をたたき、指で空を指した。
トリアンはその指先が指すところへ目をやった。
日が昇ってからあまり時間が経っていないのに、周りはだんだん暗くなっていく。
特にグラット要塞を中心に黒雲が集まっていた。
黒雲は要塞の上空で大きく渦巻いていた。
キッシュの指先が今度は要塞の向こうにある野原を指した。
遠くから砂煙が立っている。
エルフ特有の鋭い視覚によりトリアンは
その砂煙が何によって起きているのか分かった。
大規模のモンスター部隊がグラット要塞に向かって走っていた。
城門をいっぱいに開き、
まるで走ってくるモンスター部隊を歓迎しているようなグラット要塞に向かって。